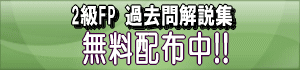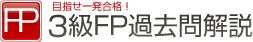問52 2022年9月学科
問52 問題文択一問題
みなし贈与財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
2.委託者が父、受益者が子である信託契約を締結し、その効力が生じた場合において、子がその適正な対価を負担しなかったときには、その信託に関する権利は、原則として子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
3.子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額を限度に、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
4.離婚による財産分与により財産を取得した場合には、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内であったとしても、その取得した財産は、原則として贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
問52 解答・解説
贈与税の課税財産・非課税財産に関する問題です。
1.は、不適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人となる場合は「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
2.は、適切。信託とは、委託者が信託契約や遺言といった信託行為により、受託者に自身の財産を移転し、受託者は委託者の信託目的に従って、受益者のために信託財産の管理・処分を行う制度です。例えば、重度の障がい者の親族が、自身の財産を信託銀行(受託者)に信託し、自身の死後も障がい者の生活を支えるために利用されます。
信託の効力発生時に、委託者以外の者が受益者で、受益者が適正な対価を負担しない場合、信託受益権は贈与税の課税対象となります。
3.は、不適切。親が所有する資産を、時価よりも著しく低い価格で子へ譲渡すると、親が子に贈与したとして、時価との差額が贈与税の課税対象となります。
4.は、不適切。離婚すると財産分与として、婚姻中夫婦が協力して築いた財産は清算して分割されますが、社会通念上相当な範囲内であれば、贈与税はかかりません。ただし、社会通念上過大であると認められる部分は、贈与税の課税対象となります。
一般的には夫婦生活におけるお互いの寄与率は50%程度とみなされるため、特段の理由なく50%超の財産分与をした場合には、超過分が贈与とみなされる可能性があるわけです。
よって正解は、2.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
![]()
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士
![]() (資格対策ドットコム)
(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
![]()
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】
![]()
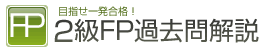
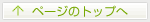
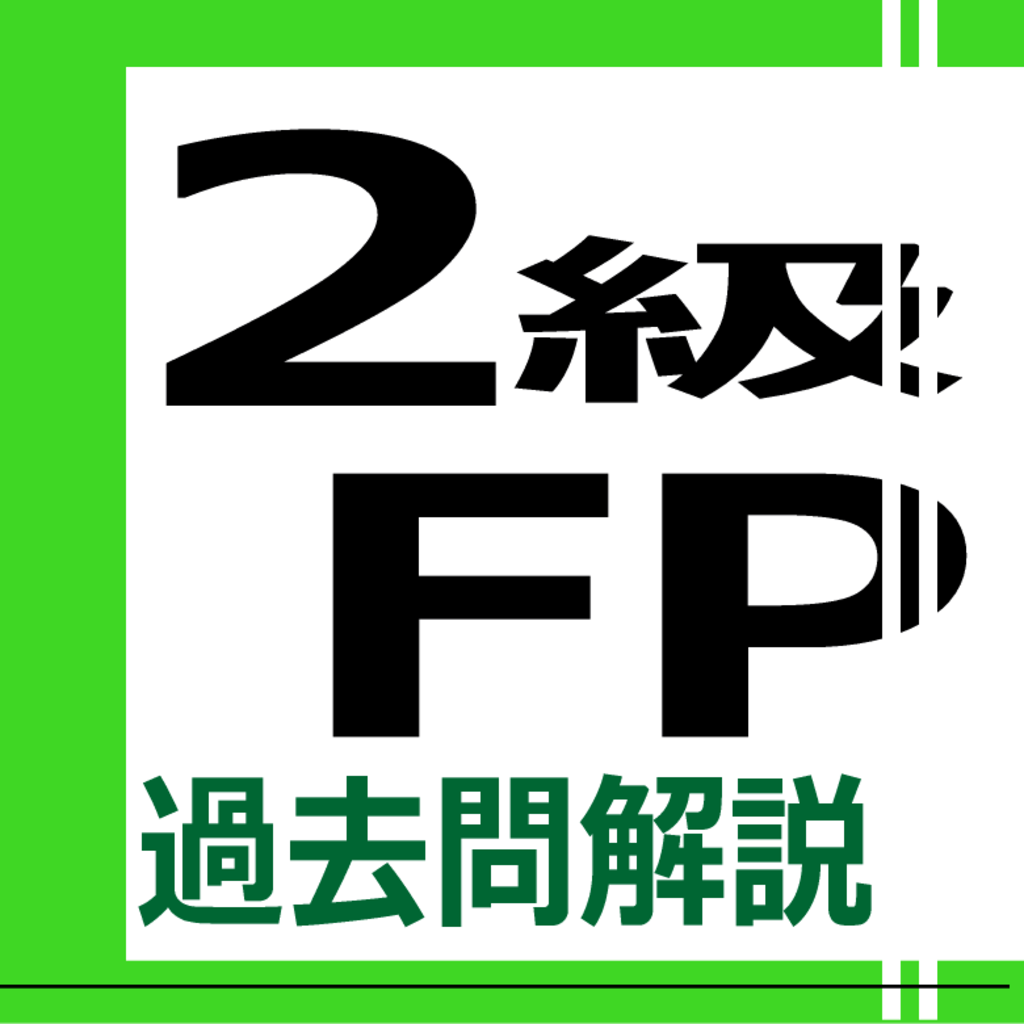 ●無料アプリ版公開中。
●無料アプリ版公開中。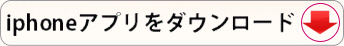
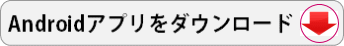
 ●広告無しの有料版。
●広告無しの有料版。