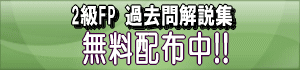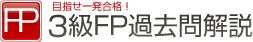問1 2019年1月実技中小事業主資産相談業務
問1 問題文
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが現時点(平成31年1月27日)で死亡した場合に、妻Bさんが受給することができる国民年金の遺族給付について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんは、所定の保険料納付要件を満たしていますので、妻Bさんには遺族基礎年金が支給されます。遺族基礎年金の年金額は、77万9,300円(平成30年度価額)です」
(2)「Aさんは、第1号被保険者としての保険料納付済期間が10年以上ありますので、妻Bさんは、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金の支給を受けることができます」
(3)「Aさんは、第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上ありますので、妻Bさんは死亡一時金の支給を受けることができます。ただし、妻Bさんが死亡一時金の受給を選択する場合は、寡婦年金の支給は受けられません」
問1 解答・解説
遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金に関する問題です。
(1)は、×。遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計。
●子の場合 :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない。
従って、子どもがいない夫婦には、配偶者が死亡しても遺族基礎年金は支給されません。
(2)は、○。国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、生計を維持されていた妻に対して、寡婦年金が60歳から65歳になるまで支給されます(10年以上継続した婚姻関係があることが必要)。
なお、平成29年8月1日以降、老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されたため、寡婦年金の支給要件である夫の保険料納付済期間も10年に短縮されましたが、遺族年金の長期要件としての受給資格期間は、以前と変わらず25年のままとなっています。
(3)は、○。国民年金の死亡一時金は、老齢基礎年金や障害基礎年金をもらわずに死亡した場合、生計同一だった遺族に支給されますが、最低3年間(36月)の保険料納付が必要です。
また、寡婦年金と死亡一時金は、受給要件をいずれも満たしている場合、どちらかを選択して受給します(併給できません)。
寡婦年金は子のない妻に対し、老齢基礎年金の支給開始まで支給されるため、通常は寡婦年金を選択したほうがトクすることが多いです。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
![]()
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士
![]() (資格対策ドットコム)
(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
![]()
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】
![]()
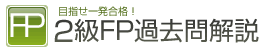
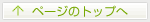
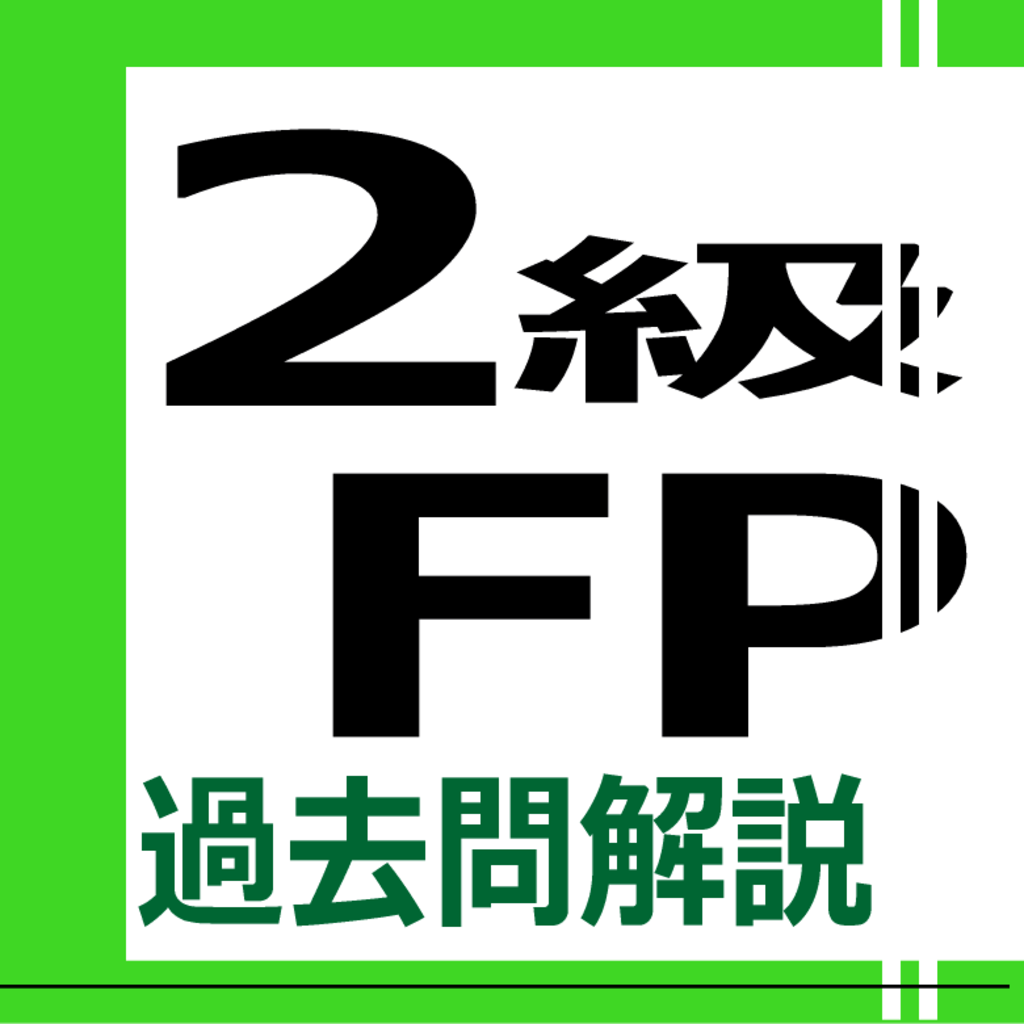 ●無料アプリ版公開中。
●無料アプリ版公開中。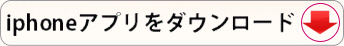
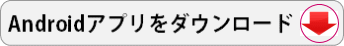
 ●広告無しの有料版。
●広告無しの有料版。