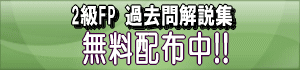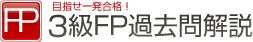問2 2019年1月学科
問2 問題文択一問題
ライフプランニングにおけるライフステージ別の一般的な資金の活用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.Aさん(22歳)は、将来のために、受け取った初任給に銀行からの借入金を加えた資金を元手として、高い収益が見込める金融商品による積極的な運用を図ることにした。
2.Bさん(30歳)は、将来のために、NISA(少額投資非課税制度)を利用して余裕資金を運用することにした。
3.Cさん(40歳)は、マイホーム購入を念頭に貯蓄を続けてきたが、預貯金の残高が増えてきたので、その一部を頭金として、住宅ローンを利用し、新築マンションを取得することにした。
4.Dさん(63歳)は、勤務先を退職後、収入が公的年金のみとなる見込みなので、資産運用についてはリスクを避け、元本が確保された金融商品を中心とした安定的な運用を図ることにした。
問2 解答・解説
世代別の資金運用・ライフプランに関する問題です。
1.は、不適切。20〜30歳代は、今後の長期的な収入と運用が見込めるため、他の世代よりも比較的リスク許容度が高いことから、余裕資金での資産運用は、有効な選択肢の1つです。しかし、借入金を活用した積極的な資金運用は、様々な投資経験を積んだ上で、自己資金とのバランスを取って実施すべきであるため、恐らく運用経験は乏しいと思われる初任給での運用は行うべきではありません。
2.は、適切。20〜30歳代は、今後の長期的な収入と運用が見込めるため、他の世代よりも比較的リスク許容度が高いことから、余裕資金での資産運用は、有効な選択肢の1つです。特に、運用益の非課税措置や掛金の所得控除といった、税制上の優遇措置のあるNISAやiDecoを活用すべきです。
3.は、適切。30〜40歳代は、一般的に子どもの教育費や住宅取得のための資金計画を立てる時期となりますが、長期の住宅ローンを利用する場合、十分な頭金を準備することで、金利や収支の変動に対するローンの返済負担を抑えることが可能です。
4.は、適切。定年退職後は安定的な収入源が公的年金だけとなり、収入額も減少してしまいますから、許容リスクが低い状態でリスクを取った資産運用を行うと、市場が暴落した際には一気にその影響を受け、生活が行き詰ってしまうため、元本確保型の金融商品による安定的な運用を心掛けることが必要です。
よって正解は、1.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
![]()
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士
![]() (資格対策ドットコム)
(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
![]()
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】
![]()
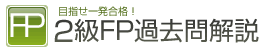
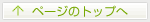
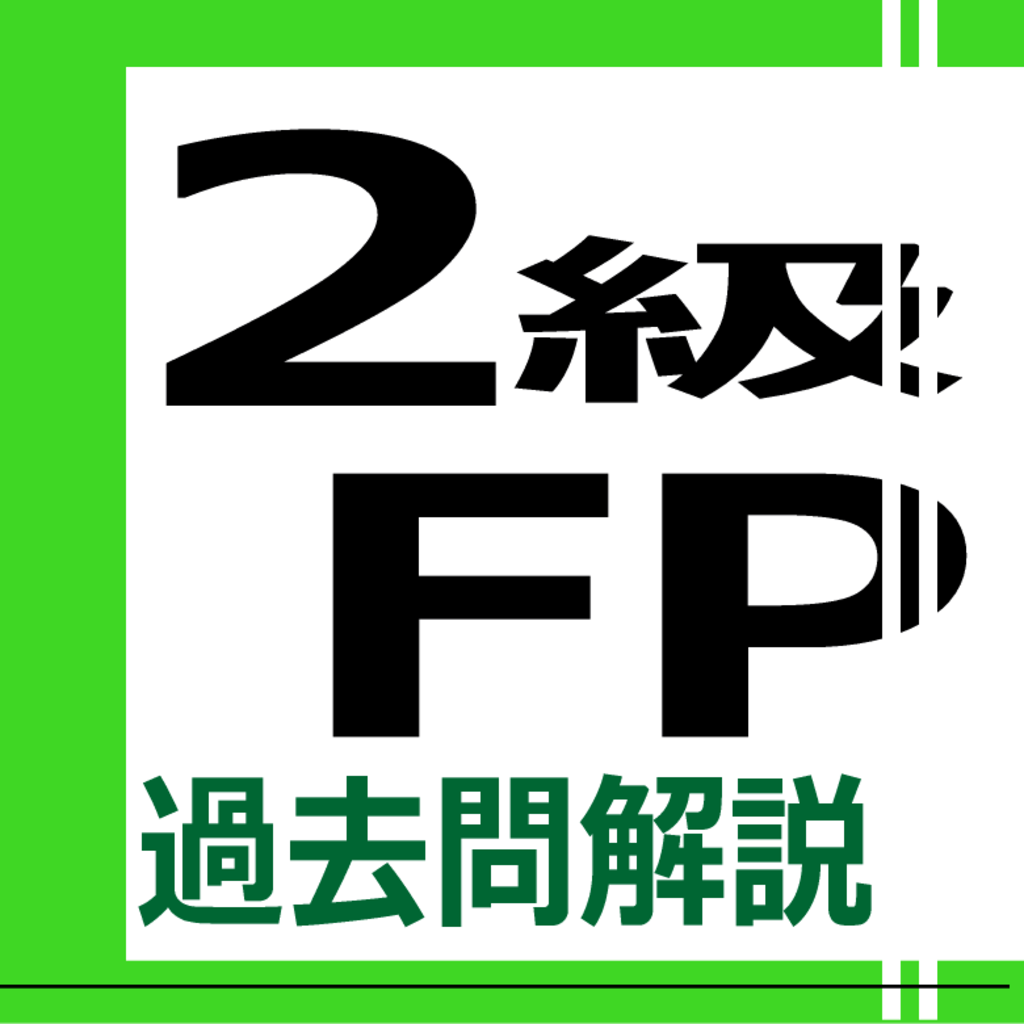 ●無料アプリ版公開中。
●無料アプリ版公開中。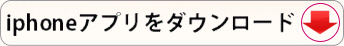
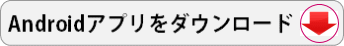
 ●広告無しの有料版。
●広告無しの有料版。