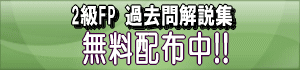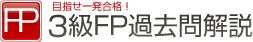問14 2017年1月実技中小事業主資産相談業務
問14 問題文
X社の自己株式の買取りに関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「X社が二男DさんからX社株式を買い取るためには、特定の株主からの取得となるため、X社の株主総会の( 1 )が必要となる。
自己株式(金庫株)の売買価額については、税法上、適正な時価に基づくこととされている。
適正な時価について、当該株式の売買実例等がなく、財産評価基本通達による評価方法に基づいて算定した価額による場合に、譲渡する個人が中心的な同族株主であるときは、発行会社が( 2 )に該当するものとして評価することになる。また、1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算にあたって、発行会社が有する土地等または上場有価証券については譲渡時における価額によること、評価差額に( 3 )を乗じて算出する『評価差額に対する法人税額等に相当する金額』は控除しないことに注意する必要がある」
〈語句群〉
イ.普通決議 ロ.特別決議 ハ.特殊決議
ニ.大会社 ホ.中会社 ヘ.小会社 ト.特定の評価会社
チ.37% リ.40% ヌ.42%
問14 解答・解説
金庫株に関する問題です。
株式を発行した会社自身が、その自己株式を取得する場合(金庫株)、特定の者から買い受ける場合には、株主総会の特別決議が必要であり、取得額は分配可能額の範囲内という制限があります。
また、会社が自己株式を取得する場合、時価であれば税法上適正な取引価格とされますが、時価とは財産評価通達による価額(相続税評価額)を参考にしつつ、一定の条件を加味して評価額を算定します。
例えば、株式を売却する個人が中心的な同族株主である場合、会社規模は小会社(乗数0.5)として評価することとされています。
この他、純資産価額方式で評価する場合、会社所有の土地や上場株式の評価を時価としたり、評価差額に対する法人税相当額の控除をしないこと、といった条件が加味されます。
なお、1株当たりの純資産価額について、数式は以下の通りです。
株価=(相続税評価額の総資産価額−負債合計額−評価差額の法人税相当額)÷発行済株式総数
※評価差額の法人税相当額=(相続税評価額の純資産額−帳簿価額の純資産額)×37%
つまり、金庫株を売買する際、中心的な同族株主である個人が売却するときは、上記計算式の「評価差額の法人税相当額」部分は算出しないで計算するわけですね。
なお、上記の法人税相当額の計算式は、平成27年4月1日から「38%」となっていましたが、法人税率の引き下げにより、平成28年4月1日からは「37%」となりました。
以上により正解は、(1)ロ.特別決議 (2)ヘ.小会社 (3)チ.37%
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
![]()
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士
![]() (資格対策ドットコム)
(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
![]()
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】
![]()
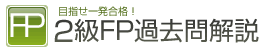
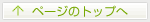
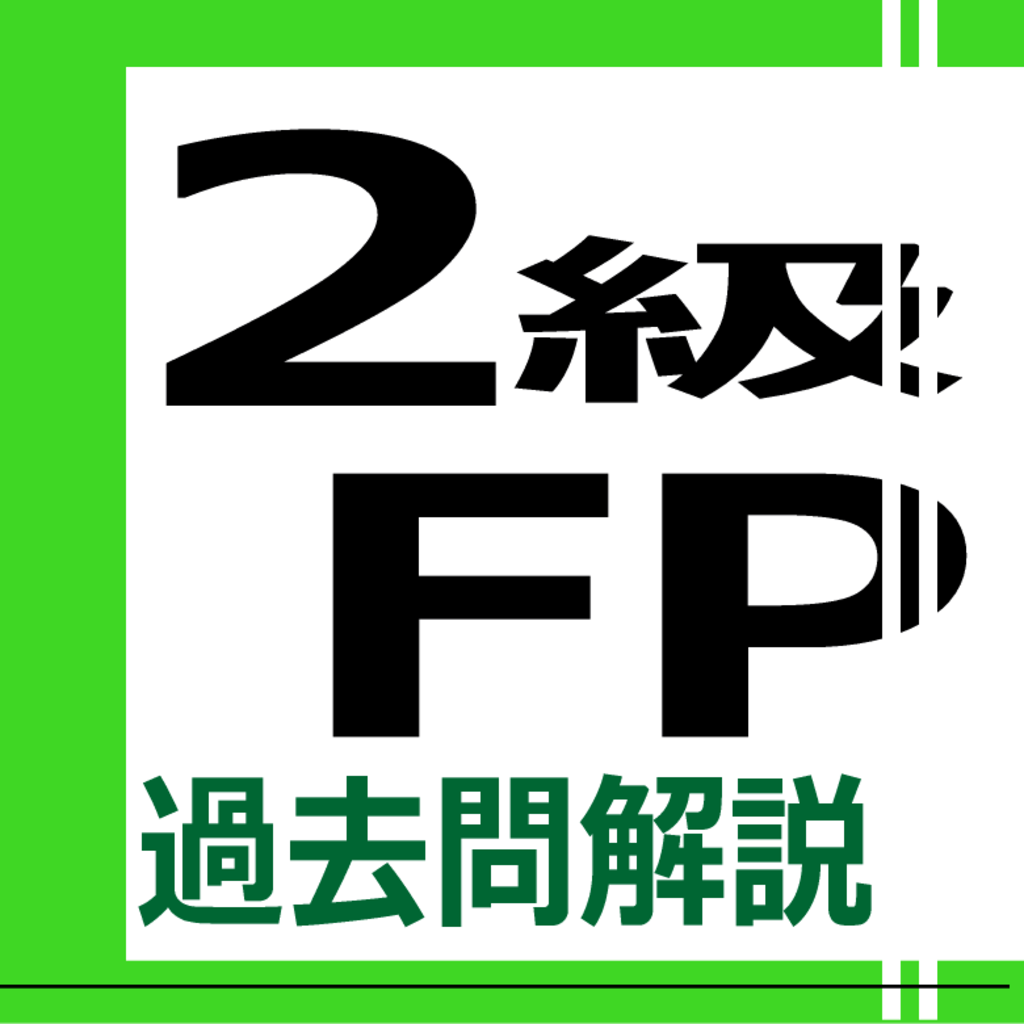 ●無料アプリ版公開中。
●無料アプリ版公開中。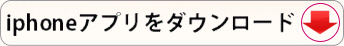
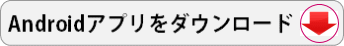
 ●広告無しの有料版。
●広告無しの有料版。