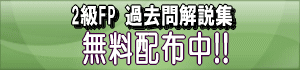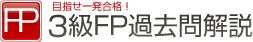問19 2019年1月実技資産設計提案業務
問19 問題文
相続の放棄をした者に係る相続税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.相続を放棄した者が、現実に負担した被相続人の葬式費用については、遺産総額から控除することができる。
2.相続を放棄した者が、遺贈により生命保険金等を取得したものとみなされる場合には、生命保険金等の非課税の規定の適用を受けることができる。
3.相続税の基礎控除額の計算における法定相続人の数は、相続の放棄をした者がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数である。
4.配偶者が相続を放棄した場合でも、その配偶者が遺贈により財産を取得したときには、配偶者の税額軽減の規定の適用を受けることができる。
問19 解答・解説
相続開始後の手続き(放棄)に関する問題です。
1.は、適切。相続放棄すると、債務控除の適用もありませんが、相続放棄した人が葬式費用を負担した場合、債務控除してもよいとされています(被相続人の債務を負担した場合には、債務控除の対象外)。
2.は、不適切。死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、相続を放棄しても死亡保険金は受け取れます。
ただし、税制上は「みなし相続財産」として、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されず、全額が相続税の課税対象となります。
3.は、適切。相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 ですが、法定相続人は相続放棄があっても、基礎控除の計算上「相続放棄はなかったもの」として扱われます。
4.は、適切。配偶者が相続放棄した場合でも、配偶者が遺贈により財産を取得したときには、配偶者の相続税額軽減(相続税の配偶者控除)を適用可能です。
例えば、被相続人に借金があったので配偶者は相続放棄。しかし、被相続人が生前に自分に生命保険をかけ、受取人を配偶者にしていると、死亡保険金は相続財産ではなく、遺贈により取得した保険金受取人の固有の財産とされ、相続税の配偶者控除を適用可能となります。
よって正解は、2
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
![]()
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士
![]() (資格対策ドットコム)
(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
![]()
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】
![]()
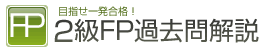
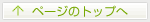
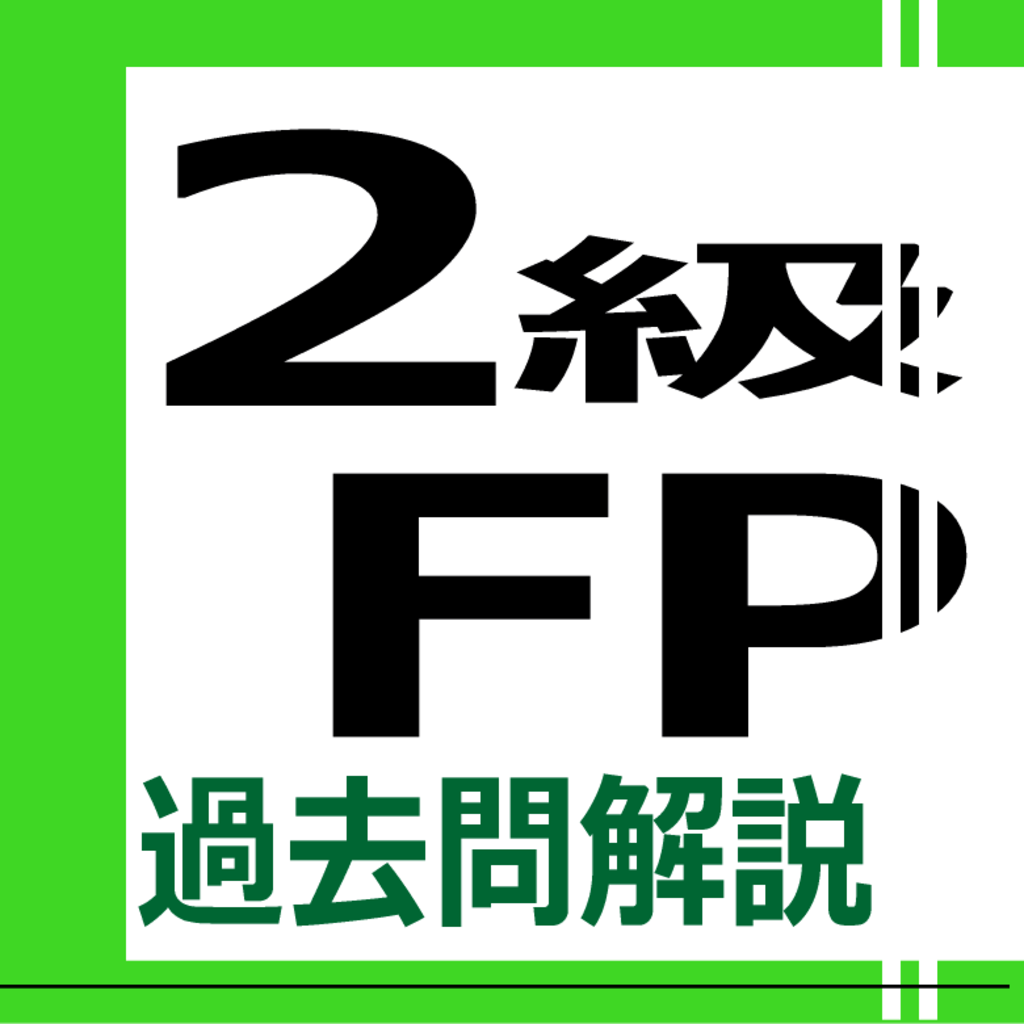 ●無料アプリ版公開中。
●無料アプリ版公開中。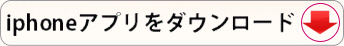
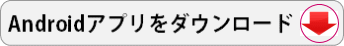
 ●広告無しの有料版。
●広告無しの有料版。